
技術の進歩や国際情勢の変化などにより、事業方針の柔軟性が求められています。その対応策として推奨されているのがDX(デジタルトランスフォーメーション)です。多くの企業がDXに取り組んでいますが、成功するとは限りません。社労士業界もDXが期待されている業界です。
そこで今回は社労士業界のDXについて詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。

DXとは
DXはDigital Transformationの略で、直訳すると「デジタルによる変革」を意味します。本来はビジネスだけでなく、広い範囲で使われる言葉です。
企業がAI・IoT・ビッグデータなどのデジタル技術を活用して業務プロセスを改善したり、新しいビジネスモデルを創り出したりするだけでなく、古いシステムから脱却して企業文化を変えることを指します。
DXを推進することは、変化の激しい時代において市場での競争優位を維持し続けるために企業が取り組むべき重要なテーマです。デジタル技術を使って社会を発展させ、人々の生活をより良くすることにつながります。
この概念は2004年にウメオ大学ストルターマン教授によって提唱されました。「進化するテクノロジーが人々の生活を豊かにしていく」というものでした。
ただし、DXは単なる変革だけでなく、デジタル技術によって既存の価値観や枠組みを根本的に覆す革新的な変化、つまり「デジタル・ディスラプション」をもたらすものであると定義されています。
社労士にとってのDX
DXが進めば社員の人事情報・スキル・キャリア・人材配置・キャリアプランの支援などが企業内で一元管理されるようになります。給与・勤怠管理など、これまでバラバラに管理されていた人事労務情報が集約されることで、人事労務業務の効率化が進みます。
また、紙からオンライン管理・クラウドサービスへの移行で業務が軽減され、人事労務担当者が本来の業務に集中できるようになります。集約された情報を活用することで、例えば、従業員のプロジェクト経験・スキルを蓄積して可視化することが可能になり、適切な人事評価・人材配置に役立ちます。
勤怠管理・給与計算・社会保険手続き・労務管理・採用・人材募集など、人事労務業務がクラウドサービスを通じて行われるようになり、データがオンラインで共有されるでしょう。
結果として社労士もクラウドサービス・DXツールを使う機会が増えます。そういった意味でも社労士の業務においても、DXへの対応は不可避な状況と言えるでしょう。

DXへの取り組みで企業からの信頼を向上させる
社労士業界においても、DXへの取り組みは重要な課題です。企業のデジタル化が進む中で、社労士の業務もDXにより情報共有・効率化など、デジタル化による多くのメリットを享受できます。DXに注力することで、社労士業務の情報管理・業務の円滑な進行が可能となります。
具体的には、社員情報・労働契約書などの重要な文書をデジタル化し、適切なファイル管理システムを使用することで、情報漏えい・データ紛失のリスクを軽減できます。また、業務時のコミュニケーションが改善され、迅速かつ正確な情報共有が可能になります。これにより、企業の業務効率が向上し、企業からの信頼を得ることができます。
社労士としてDXに積極的に取り組むことで、業界の発展に貢献できるだけでなく、顧客企業からの信頼獲得にもつながります。
今後も企業のデジタル化に対応し、より高度なサービスを提供していくことが求められています。
社労士にとっての今後の課題
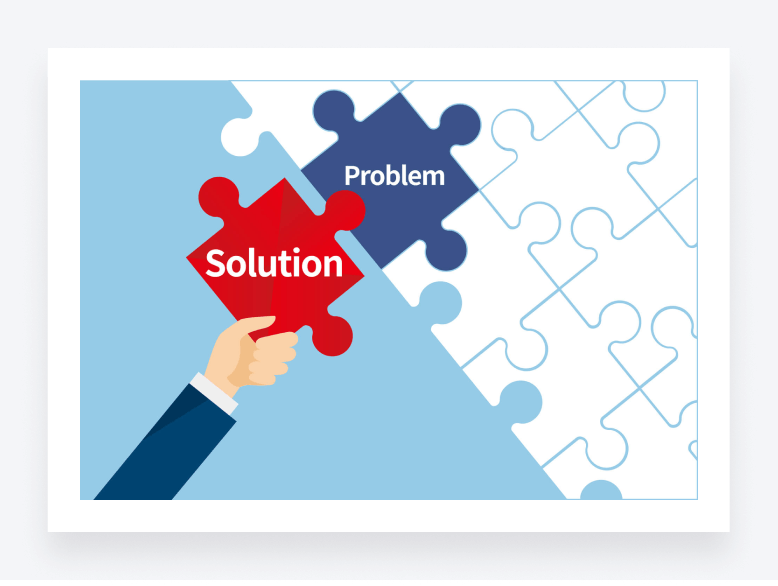
社労士事務所では、細かな事務作業を所長や有資格者が担っているケースがあり、社労士が本来提供すべき価値を十分に提供できていない面があるとされています。例えば、所長が書類作成の多くを行うなど、資格のないスタッフでも対応できる業務を所長や有資格者が担当していることがあります。
電子申請やツールの進化が進んでいるにもかかわらず、このような現状が続いているのは、士業のビジネスの特性によると考えられます。士業は法的に定められた業務を確実に遂行することが求められるため、変化を前向きにとらえにくい面があるのかもしれません。
顧客が求めているのは書類作成ではなく、経営・人事に関する課題の解決です。顧客のニーズに応えるために、事務所内で役割を明確に分担することやIT技術を活用しての業務負担の軽減が大切です。
手作業にかかる時間を減らすことで、営業・マーケティングなど事務所の成長戦略に時間を割けるようになります。顧客への価値提供だけでなく、事務所自身の成長にもつながるため、効率化できる無駄な業務は行わないというスタンスを持ち、担当する業務を見直していくことが重要です。
社労士の支援による働き方改革への対応で社員満足度の高い企業へ
最近では、働き方改革が注目を集めており、企業には社員の満足度を高めることが求められています。多くの企業が積極的に働き方改革に取り組んでおり、成功しているケースも多く見られます。
社労士の対応分野では、従業員の働き方・労働環境の改善が重要なテーマとなっています。例えば、柔軟な勤務形態を取り入れて従業員のワークライフバランスを改善した企業では、社員の定着率・生産性が向上し、その結果として社員の満足度が高まることもあります。
社労士として企業の労働環境・制度を評価し、適切なアドバイスを提供することで、働き方改革に貢献できます。その結果、企業と従業員の双方にとって有益な環境が整い、企業の競争力向上にもつながります。
働き方改革に取り組む企業の内で社員の満足度が高い企業も存在します。その実現には社労士の支援が大きく関わっていると言えます。
今後も、社労士と企業の連携によって、さらに多くの働き方改革が実現されていくことが期待されます。
スキル向上に注力し高品質なコンサルティングを提供
社労士は労務問題・社会保険・労働保険などに関する法律の知識や経験を持っています。しかし、それだけでは高品質なコンサルティングを提供することは難しいです。社労士がスキルアップを図り、より専門的で価値のあるアドバイスをすることが必要です。
スキルアップとは、自己研鑽によって知識や技術を向上させることです。社労士の場合、最新の制度・法律の改正を常に把握することは不可欠です。また、問題解決力・コミュニケーション能力・クライアントのビジネスへの理解など、多様なスキルの向上が求められます。
これらのスキルアップによって、社労士はクライアントの問題に迅速かつ正確に対応できるようになります。その結果、クライアントに高品質なコンサルティングを提供でき、信頼関係も築くことができます。
スキルアップに力を入れ必要な研修・セミナーを提供して、クライアントに適したアドバイスができるように努力している社労士は少なくありません。高品質で信頼できるコンサルティングを提供するためには、継続的なスキルアップが欠かせないと言えます。
社労士業務に大きく関係のある電子申請
ここで改めて、社労士業務におけるDXの影響として大きく関係のある、電子申請について考えてみましょう。
既に労働社会保険関連の手続きの多くは電子申請で行うようになっています。社会保険・労働保険の手続きに関しては、2020年4月から資本金が1億円を超える企業で電子申請が義務化されています。
またe-Gov電子申請を使うことで、行政への申請・届出・処理状況の確認・公文書のダウンロードなどの業務が可能です。このサービスをすでに利用している社労士も少なくありません。
ただし、電子申請を利用することで書類を郵送する手間や窓口に持っていく時間は削減されますが、書類作成や進捗管理にかかる労力は残ります。これを軽減するためには、クラウド型の業務マネジメントツールなどを活用すると良いでしょう。導入することで業務の効率化が進み、メリットが大きくなります。
DX推進のポイント
DXの推進を成功させるためには以下のポイントが重要です。
目的を設計する
自事務所のビジョンや事業戦略と連携した具体的な目標を設定し、デジタル技術の活用方法を検討するプロセスが重要です。具体的な目標を設定することで組織全体の意識を統一し、必要以上にハイエンドなツールの導入を避けられます。
所長社労士が主導する
DXはビジネスモデルや企業文化の変革を伴います。そのため、所長社労士が主導して目的やビジョンを明確にし、部門横断的にDXを進めることが必要です。
自社の課題と結びつける
DXは新たな技術を導入するだけでなく、自社の課題を解決するための手段としてデジタル技術を活用することが重要です。現状の課題を洗い出し、それに対する解決策を検討します。
マインドを醸成する
組織全体がデジタル技術を活用して変革を起こすマインドを持つことが必要です。変革を起こすためのオープンなマインドや新しい試みを積極的に取り入れる文化を作ります。
DX推進体制を構築する
DXには専門的なチームを設置し、全社的な取り組みとして経営層直下のプロジェクトにすることが理想的です。また、デジタルリテラシーと変革に対する積極的なマインドを持つ人材の確保が欠かせません。
PDCAを徹底する
小規模なプロジェクトから始めて結果を評価・改善し、PDCAサイクルを確立します。小さな成功体験を積むことで、DXに対する抵抗を減らし、長期的に推進します。
以上のポイントを意識しながらDXを推進することで、効果的なデジタル変革が実現できます。
まとめ
経済産業省が指摘した「2025年の崖」が近づいている中で、DXで成果を出している企業はまだ少ないのが現状です。しかし、コロナ禍以降、ビジネスとデジタルの関係はますます重要になっており、消費者も安全性や利便性の向上を求めて企業のデジタル化に期待しています。
本記事で紹介したように、DXを実現するための様々なソリューションがあり、補助金の活用も可能です。まずは自社の経営課題や将来のビジョンを検討し、自社に適したDXの形を考えることから始めてみましょう。
社労士事務所がDXを推進していく上では「TaxDome(タックスドーム)」の導入がおすすめです。
「TaxDome」は士業事務所の業務管理を効率化するために開発されたクラウド型ツールです。プロセスの自動化を中心に据え、世界中で採用されています。現場のニーズに応えた機能が豊富に備わっており、業務改善をワンストップでサポートします。直感的で使いやすいインターフェースも特徴の一つです。
ぜひ導入をご検討ください。

eBookが送信されました。メールをご確認ください。
エラーが発生しました。再度お試しください。



