
資格にはいろいろなものがありますが、その中でも社労士は非常に人気のある資格です。しかし、その具体的な仕事内容については、あまり知られていないかもしれません。そこでこの記事では、社労士の仕事内容・就職先・やりがいなどについて詳しく解説します。社労士についての理解を深め、資格取得を目指す際の参考にしてみてください。
社労士とは?
社労士(社会保険労務士)は企業経営における「人・物・お金・情報」という4大要素の中で、特に重要な「人」に焦点を当てた専門家です。経営の効率化を図るために、人事・労務管理全般に関する問題を見つけ出し、解決策を提案します。また、少子高齢化社会における医療保険や年金制度の変革に関する相談にも応じます。今後ますます人の問題が重要性を増すと考えられる時代において、人に関するさまざまな問題に焦点を当てる社労士の役割はとても重要になっています。

社労士の仕事とは?
社労士は、社会保険や年金、労働管理などを担当する専門家です。複雑な社会保障制度、特に年金などを円滑に活用できるようサポートします。また、経営者と労働者の間で良好な関係が築けるように助言や相談に応じます。
社会保険労務士(社労士)の業務は、1号業務、2号業務、3号業務と大きく3つに分かれます。特に1号業務と2号業務は社労士にしか許されていない「独占業務」です。
それぞれの業務について詳しく説明します。
手続きの代行(1号業務)
1号業務に分類される手続き代行は、社労士にしか許されていない独占業務の一つです。これは、健康保険・雇用保険・厚生年金などに関連する書類の作成や、書類を労働基準監督署などの行政機関に提出する代行業務です。社労士がこれらの業務を行うことで、手続き上のミスや法令違反を防ぐことができます。企業が従業員との信頼関係を維持するためには、これらの業務が非常に有効です。
労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成(2号業務)
社労士による帳簿書類の作成も、労働社会保険諸法令に基づく独占業務の一部です。企業は就業規則・労働者名簿・賃金台帳などを労働社会保険諸法令に基づき作成する必要がありますが、これらの文書を法令に準拠して作成するのが社労士の役割です。
法律の専門知識なしに帳簿書類を作成すると、法的な規制を逸脱する可能性があります。帳簿書類は企業の基本的な文書であり、その作成には法律の専門家である社労士が関与することが一般的です。
人事労務管理のコンサルティング(3号業務)
最近では、雇用形態が多様化し、正規雇用者だけでなく、契約社員やパートタイマーなどが増加しています。このような変化に伴い、人事労務の問題も複雑化し、企業内で解決が難しい場合もあるでしょう。こうした状況で頼りになるのが社労士であり、専門家としてアドバイスやコンサルティングを提供します。
人事労務管理のコンサルティングは、社労士の独占業務ではありませんが、複雑な状況においては専門的な判断が求められることがあり、その際にはプロの社労士のアドバイスが不可欠です。
社労士の働き方
社労士としてのキャリアを積んでいくには、いくつかの方法が考えられます。また、社労士の場合、他の士業とは異なる特別な働き方が認められています。社労士のキャリアや働き方について、詳しく見ていきましょう。
個人事業主として独立開業する
社労士としての働き方の中で、最も一般的で分かりやすい方法は、独立して個人事業主として活動することです。これは、自身の事務所を開設し、クライアントを獲得し、さまざまなニーズに対応するという方法です。個人事業主としての働き方は比較的自由度が高い反面、経理から営業まで全てを自己で行う必要があり、収入が不安定な側面もあります。
個人事業主としての活動を始めるには、まず各都道府県の社労士会に登録しなければなりません。そして、この登録には社労士試験に合格した上で、2年以上の実務経験が必要です。ただし、実務経験が不足している場合でも、社会労務士会が主催する研修を受講することで、実務経験の一部として認められることがあります。
個人事業主として活動する際の開業資金は、予定する業務内容によって異なります。社労士会への登録料は必要ですが、事務所を借りるかどうか、従業員を雇用するかどうかなどの判断は個々の事業主に委ねられます。
社労士の資格があれば個人事業主として活動することは可能ですが、その後の収入は個々人の準備や能力次第です。したがって、事業を開始する前に十分な準備をしておくことが望ましいでしょう。
勤務社労士になる
次に、社労士の資格を持ちながら、企業に就職して社員として働く方法について説明します。社労士が他の士業と異なる点はここにあります。行政書士など他の士業の資格を持つ者が企業に就職した場合、その企業内で自身の資格を生かした業務を行うことはできません。
つまり、行政書士の資格を持った人が就職した場合、行政書士の肩書きは使用できません。そのため、行政書士としての特定業務を行うことはできず、あくまで自身の知識を業務に生かすことに留まります。
しかし、社労士の場合は、その業務内容が企業の業務と密接に関連しているため、就職しながらも社労士業務を行うことが可能です。ただし、企業の社労士が使用できるのは、その企業内での業務に限定されており、他社からの業務委託を受けることはできません。
一般的には、大企業などが社内の労務管理・事務処理・労働紛争の解決などのために社労士を配置して活用しています。
社会保険労務士法人で雇用される
社労士としてのキャリアパスの一つとして、社会保険労務士法人での雇用も考えられます。社会保険労務士法人は、社労士が設立できる法人であり、そこで働く社労士は全員が理事です。そして無限責任を負うことになります。
無限責任は連帯責任ともいえます。つまり、同じ社会保険労務士法人に所属する他の社労士がミスを犯した場合、その法人に登録している全ての社労士は責任を均等に負うという考え方です。
社労士法人での雇用は、個人開業を目指すがまだ準備が整っていない人や、将来的に独立開業を目指すために社労士としての実務経験を積みたい人に適しています。ただし、非常に重い責任を負うため、業務に対する高い意識が求められます。
社労士の仕事のやりがいは?

この章では社労士の仕事のやりがいについて解説します。
顧客にとって頼りになる相談相手になれること
社労士のクライアントは通常、企業の経営者です。社労士には独占業務があり、企業の成長に不可欠なパートナーとして経営者から信頼されます。
また、雇用に関するアドバイスを提供する立場にあり、労働相談やコンサルティング業務を通じて、働きやすい環境の構築を支援し、企業の発展に貢献しています。
さまざまな労働者のサポートを提供できること
企業に限らず、現場でも多様な労務関連の問題が発生しています。社会保険や年金制度などについて、十分に理解していないという労働者は少なくありません。例えば、業務中の怪我が補償されるのか、どの健康保険に加入しているのか、会社が倒産した場合の失業保険の受給額など、十分な知識がないために活用できない場面もあります。
社労士がこうした悩みを抱える労働者に対して支援を提供することで、非常に大きな達成感を得られるケースもあるでしょう。
自身の努力次第で高い収入を得られること
社労士は通常、独立開業を選ぶことが一般的であり、自己の努力と能力によって大きな成長を遂げることができます。特に法人クライアントを獲得できれば、収益は増加し、事務所の規模の拡大もかなうでしょう。
信頼される仕事を行い、成果を上げて顧客を獲得することで、報酬という形で自身に還元されます。この達成感は、独立開業ならではのものかもしれません。
専門性の高い仕事を通じて尊敬される存在になれること
社労士は国家資格であり、関連法令に基づく申請書の作成や手続き代行など、社労士にしか行えない独占業務が定められています。このような特権は、自身のキャリアにおいて大きな利点となるでしょう。
また、労働保険・社会保険の手続き・雇用に関する助成金の申請など、社労士が担当する業務は企業にとって極めて重要です。専門的なスキルを十分に発揮し活躍することは、社労士にとって大きなやりがいとなります。
社労士の将来性は?
近年、ITやシステム化の進展により、業務の効率化が進み、社労士の業務が減少しているとの指摘があります。企業が経費削減を行う中で、これまで社労士が担ってきた業務を自己処理する例も見受けられます。しかし、働き方改革の推進や企業競争の活発化に伴い、社労士の需要はむしろ高まっているとも考えられるのです。この章では社労士の将来性について解説します。
一部の業務は減少傾向に?
労務管理の「人事」と「労務」は、従業員と労働に関連する業務を指します。社労士の1号業務と2号業務は独占業務です。しかし、管理ソフトの普及や電子申請の促進により、これらの業務の手間が大幅に減少しています。
従業員がソフトウェアに必要事項を入力するだけで申請できるようになったため、企業は社労士を通さずに業務を進めることも可能です。政府も電子申請を促進しており、1号業務と2号業務の需要は今後減少すると予測されています。
社労士コンサルティングの需要が高まっている
企業が抱える人事・労務面の課題としては、人材育成・多様な雇用形態への対応・賃金や年金制度などが挙げられます。
こうした課題に対し、社労士が適切なアドバイスを提供し、課題解決に導くコンサルティング業務については需要が高まっているでしょう。また、助成金の申請に関する相談も増加しているとされています。助成金の申請は複雑なことも少なくなく、企業の担当者が理解しきれないケースもあるのです。
社労士のコンサルティングを受けることで、申請方法の助言が得られます。代理申請も可能です。
AIによる代替の可能性
社労士の1号業務や2号業務が管理ソフトにより企業自身で行われる動きが進んでいますが、これらの業務は今後AIに置き換えられる可能性も高いといわれています。ただし、3号業務は人間同士のコミュニケーションが不可欠なため、AIに代替される可能性は低いでしょう。
将来に向けての対策
社労士の業務がAIに置き換えられないようにするためには、企業担当者や従業員との密なコミュニケーションが重要です。働き方改革に伴い、企業は働き方の見直しを余儀なくされるでしょう。AIは業務効率化に一役買いますが、そのプロセスにおいて社労士の役割は欠かせないといえます。
社労士としてはAIを活用しながらも、コンサルティングに力を入れて企業の課題解決を図る姿勢が求められます。
社労士になるには?
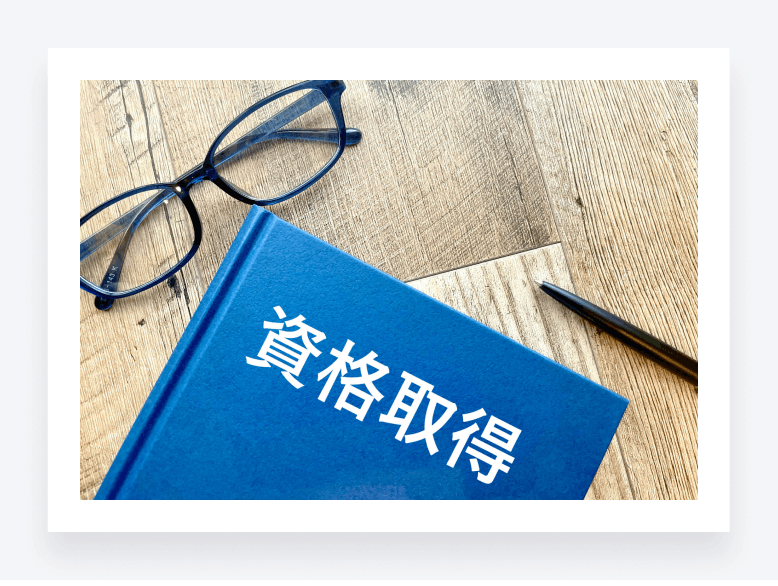
社労士は国家資格の一つであり、その取得には国家試験に合格する必要があります。この章では受験資格や試験科目について詳細をご説明します。
【受験資格】
社労士試験を受験するための主な条件は以下の通りです。いずれか一つでも満たしていれば社労士試験を受験できます。
- 大学・短期大学・専門職大学などの卒業者
- 全国健康保険協会、日本年金機構、社労士事務所などで3年以上の実務経験がある者
- 司法試験の予備試験、行政書士試験、厚生労働大臣が認定する国家試験に合格した者 など
【試験科目】
試験科目は以下の通りです。
- 労働基準法及び労働安全衛生法
- 労働者災害補償保険法
- 雇用保険法
- 健康保険法
- 厚生年金保険法
- 国民年金法
- 労務管理その他の労働に関する一般常識
- 社会保険に関する一般常識
試験は選択式と択一式の問題で構成されており、各科目につき選択式は5点、択一式は10点(一般常識は両者合わせて10点)の配点があります。法律科目では各科目の細部まで把握する必要があり、一般常識科目は幅広い範囲から出題されるため、対策が難しいとされています。
合格基準点は科目ごとに設定されており、どの科目も基準点をクリアしなければ合格とは見なされません。合格基準点は難易度によって異なりますが、平均的に点数を確保することが求められます。
まとめ
今回は、社労士の仕事内容や社労士になるための方法について詳しくご紹介しました。社労士は社会保険と労務の専門家です。中小企業の経営者やさまざまな職業の従事者から多くの相談を受けることがあり、独立開業や一般企業への就職など、さまざまな働き方があります。また社労士試験は難関ですが、働きながらでも合格を目指す方もいらっしゃいます。
社労士の仕事内容は多岐にわたり、独立して活躍することも、企業内でその資格を役立てることも可能です。そのため、さまざまな業界から高い需要があり、幅広い活躍の場があります。将来性も十分にある資格であるといえるでしょう。
また、近年、社労士が業として成功する鍵として、「DX化」の必要性が叫ばれています。
「TaxDome(タックスドーム)」は、社労・税務・会計・法律を含む、世界の士業オペレーション現場で使われている、アメリカで生まれた士業のための業務マネージメントDXツールです。
これから社労士を目指す方は、DXへの対応状況を付加価値のひとつとして大いにアピールできるよう、事務所内でのスタッフとの仕事や、顧客に対してのサービス提供等、ありとあらゆる場面で、「TaxDome」に代表されるDXツールが使われることを前提に、資格受験対策や研修に取り組むことがオススメです。

eBookが送信されました。メールをご確認ください。
エラーが発生しました。再度お試しください。



