
税理士・社労士といった資格名を一度は聞いたことがある方もいらっしゃることでしょう。しかし、具体的な業務内容や資格の取得難易度についてはあまり詳しくない方も少なくないかもしれません。
そこでこの記事では、税理士と社労士の違いや自分がなりたい場合にどちらを選択すべきかなどについて説明します。税理士や社労士という職業に興味がある方に、ぜひご参考にしていただければと思います。
税理士と社労士の相違点
税理士と社労士は、それぞれ税務と労務管理の専門家として知られています。税理士の主な仕事は、企業・個人に対しての納税方法・節税策の助言や税務申告書の作成・提出など税務に関する業務です。税理士は税法・財務に関する知識に長けており、法律・規制の変更にも常に対応しながらクライアントの税務上のニーズに応えます。
一方、社労士は企業の人事労務管理において重要な役割を担っています。従業員の労働条件・労働法令に基づく規定に関するアドバイスを提供し、雇用契約・労働規則の作成・改訂、労働紛争の解決などを行うのが主な業務です。また、社会保険・労働保険などの手続き・管理にも携わります。さらに、人事制度の改善や労働環境の整備など、従業員の福利厚生・労働条件の向上にも貢献します。

税理士と社労士はそれぞれ異なる専門領域を持ち、企業・個人のさまざまなニーズに対応するために重要な役割を果たしています。税理士と社労士の専門知識・経験を活用することで、クライアントは税務・労務管理に関するさまざまな課題・リスクに対処し、ビジネスの成長・発展を促進できるのです。
業務内容の違い
税理士の業務内容は以下の通りです。
- 税務業務(独占業務):税務書類の作成、税務代理、税務相談など
- 会計業務(税務業務に関連することが多い):会計帳簿の記帳や財務諸表(決算書)の作成など
- その他の業務:経営コンサルティング(経営計画や財務戦略の策定)、相続・事業承継、IPO、M&A、国際税務など
一方、社労士の主な業務は以下の通りです。
- 労働社会保険の手続き:法改正に対応した手続きや各種助成金の申請など
- 労務管理の相談と指導:雇用管理、人材育成、人事、賃金、労働時間などに関する相談やアドバイス
- 年金に関する相談:加入期間・受給資格の確認など
- 紛争解決手続きの代理(※特定社労士のみ):裁判に頼らない紛争解決手続きの代理
- 補佐人の業務:弁護士と協力して裁判所に出頭し意見陳述を行う業務
税理士と社労士の難易度比較
この章では、税理士と社労士の資格取得の難易度を受験資格・試験内容・必要な学習時間などについて比較します。
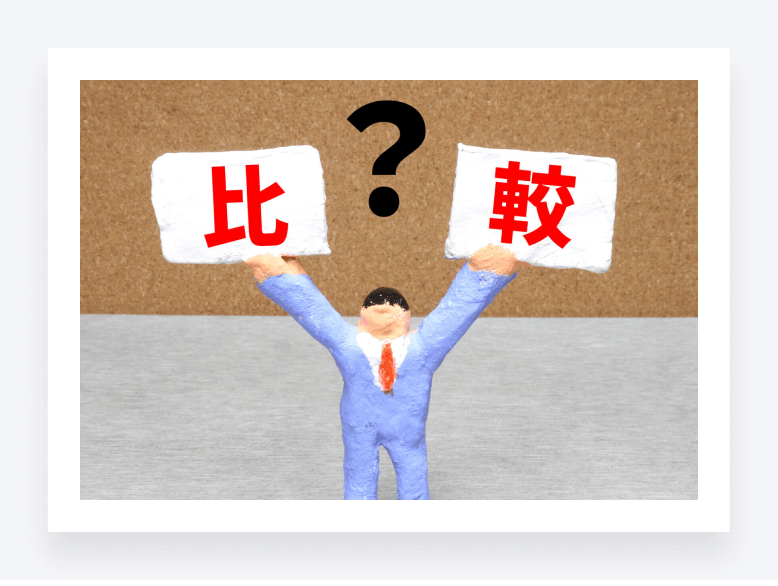
受験資格から見る難易度
税理士の主な受験資格は以下の通りです。なお税法に属する試験科目に限ります。会計学に属する試験科目については、令和5年度の試験より受験資格の制限がなくなりました。
税理士の受験資格1(学識による受験資格)
- 大学、短大、または高等専門学校を卒業し、社会科学の科目を1科目以上履修した者
- 大学の3年生以上で、社会科学の科目を含む62単位以上を取得した者
- 一定の専修学校の専門課程を修了し、社会科学の科目を1科目以上履修した者
- 司法試験に合格した者
- 公認会計士試験の短答式試験に合格した者
税理士の受験資格2(資格による受験資格)
- 日商簿記検定1級合格者
- 全経簿記検定上級合格者
税理士の受験資格3(職歴による受験資格)
- 法人または個人事業主の会計事務に2年以上従事した者
- 銀行、信託会社、保険会社などで資金の貸付けや運用に関する事務に2年以上従事した者
- 税理士、弁護士、公認会計士などの業務の補助事務に2年以上従事した者
上記のいずれかの要件を満たすことで、税理士の受験資格を得ることができます。その他にも、別途受験資格が認められるケースもあります。
一方、社労士の主な受験資格は以下の通りです。
社労士の受験資格1(学歴)
大学、短大、高等専門学校を卒業した者
学校教育法に基づき短大卒以上の学力があると認められた者 など
社労士の受験資格2(国家資格)
例えば行政書士、弁理士、税理士、司法書士の国家試験に合格した者 など
社労士の受験資格3(実務経験)
- 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人で、役員または従業者として3年以上勤務した経験がある者
- 公務員、全国健康保険協会、日本年金機構の役員などとして3年以上勤務した経験がある者
- 社会保険労務士または弁護士の業務を補助する事務に従事した期間が3年以上ある者
- 労働組合の役員や会社役員として3年以上の労務経験がある者
- 労働組合の職員や会社の従業員として、労働社会保険諸法令に関連する事務を3年以上経験した者 など
試験内容から見る難易度
社労士試験は、選択式試験と択一式試験の2つの形式があり、両方ともマークシート形式です。一方、税理士試験では、必修科目、選択必修科目、選択科目の3つの区分があり、全11科目のうち5科目に合格することで試験に合格します。
税理士試験には免除制度があり、以下の条件で科目免除が適用されます。
税理士試験の資格による試験免除
- 弁護士:全科目
- 公認会計士(一部研修が必要):全科目
税理士試験の学位取得による科目免除
- 平成14年3月までに大学院に進学し、商学の学位(修士または博士)を持つ者:会計系の科目
- 平成14年4月以降に大学院に進学し、会計系または税法系の修士論文を執筆し、それぞれの科目に1科目以上合格した者
会計学に属する科目などの学位を持つ者:会計系の科目
税法に属する科目などの学位を持つ者:税法系の科目
- 平成14年4月以降に大学院に進学し、会計系または税法系の博士論文を執筆し、それぞれの科目に1科目以上合格した者
会計学に属する科目などの学位を持つ者:会計系の科目
税法に属する科目などの学位を持つ者:税法系の科目
税理士試験の国税従事による科目免除
- 10年もしくは15年以上税務署において勤務した国税の従事者:税法系の科目
- 23年もしくは28年以上税務署に勤務して、指定の研修を修了した国税の従事者:会計系の科目
合格までの平均勉強時間
社労士試験の合格に向けた一般的な学習時間は800〜1,000時間程度といわれています。一方、税理士試験では科目ごとに必要な学習時間が400時間から600時間とされており、全体の学習時間は2,000時間以上に及ぶため、学習の難易度は高いといえるでしょう。
税理士と社労士に向いている人
この章では、税理士と社労士のどちらを目指すか迷っている方に向けて、各資格に向いている方について解説します。
税理士に向いている人
税理士は税務や会計に関するアドバイスを提供する専門家です。具体的には、複雑な税務書類の作成や解釈などが主な業務です。そのため、微細な数値の違いに気付く高い注意力を持ち、会計処理における計算能力が高い人が税理士に向いています。
社労士に向いている人
社労士は労働環境や労務状況に関するアドバイスを行う専門家です。言い換えれば、人々の福祉向上に寄与する役割を果たします。そのため、コミュニケーション能力が高く、他者との共感を持ちやすい人、また、人との対話を楽しむことが得意な人が社労士に向いているでしょう。
まとめ
社労士と税理士の業務内容にはあまり共通点が見られませんでしたが、受験資格や学習時間には共通している部分があります。試験科目や試験制度などの試験内容は大きく異なり、特に社労士の合格基準点や税理士の科目合格制度の違いは、両者の合格難易度に影響を与えていると考えられるでしょう。平均勉強時間に関しては、税理士試験のほうが多い傾向にあります。
一発合格を目指す場合、税理士試験の難易度は極めて高いといえます。一方で複数回受験が前提となる場合、税理士試験には科目合格制度があるため、難易度は下がるでしょう。しかし、社労士試験にはそういった制度がなく、一発合格しか選択肢がないため、場合によっては社労士試験のほうがより難易度が高いといえます。
何より重要なのは、自分の興味や適性に合った資格を選択することです。両試験とも難関であることは間違いありませんので、自己の能力や目指す業界との適合性を考慮して選択することが望ましいでしょう。
どちらも専門性が高い職業ですが、資格を超える付加価値を顧客に提供できるかどうかが、プロの税理士・社労士として成功をするための重要な鍵となります。
また、士業における付加価値のひとつとして、「DX」が世界的に推奨されています。
「TaxDome(タックスドーム)」は、世界の士業オペレーション現場で使われている、アメリカで生まれた士業のための業務マネージメントDXツールです。
これから税理士や社労士を目指す方は、DXへの対応状況を付加価値のひとつとして大いにアピールできるよう、事務所内でのスタッフとの仕事や、顧客に対してのサービス提供等、ありとあらゆる場面で、「TaxDome」に代表されるDXツールが使われることを前提に、資格受験対策や研修に取り組むことがオススメです。

eBookが送信されました。メールをご確認ください。
エラーが発生しました。再度お試しください。



