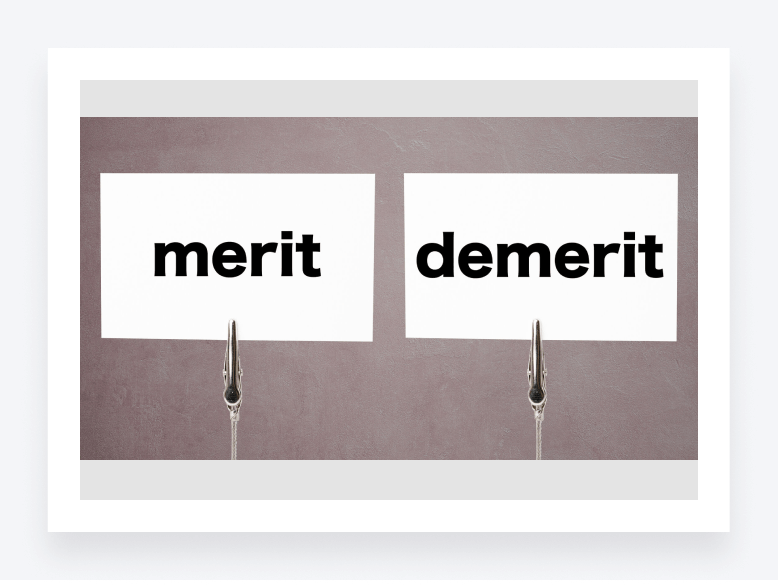給与計算は複雑な業務であるうえに、法令を守ることが求められるため、専門知識がなければ上手くいかないことが想定されます。また、従業員数の増加によって担当者の負担が増加する業務でもあります。
最近では給与計算のアウトソーシングも一般的になっており、外部委託先としては会計事務所や社会保険労務士が選ばれることが少なくありません。
そこでこの記事では、給与計算を会計事務所や社労士に依頼する際のメリット・デメリット、業務内容の違いなどを詳しく解説します。給与計算の負担を軽減し、専門的な知識による正確な処理を求めている方は、ぜひ参考にしてください。
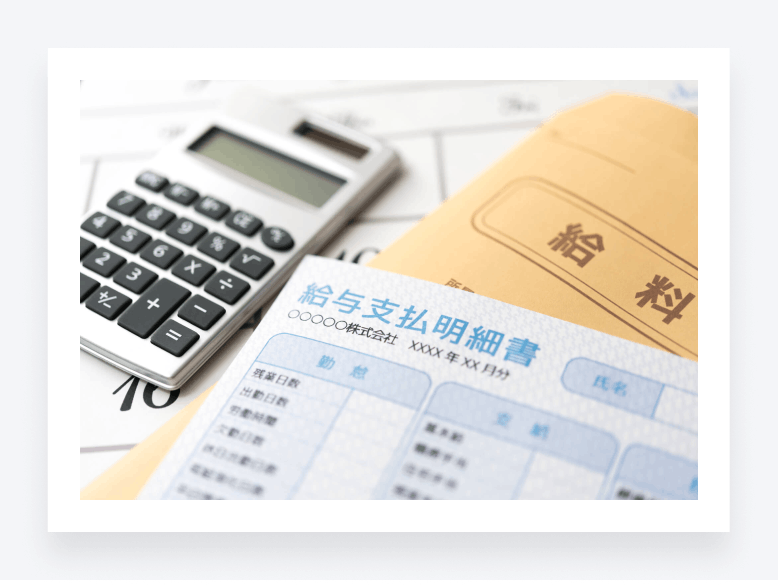
給与計算のアウトソーシング
給与計算には毎月の給与計算・支払い・年末調整・住民税の計算など、年間を通してさまざまな業務があります。この章ではこれらの業務についてアウトソーシングできる範囲を解説します。
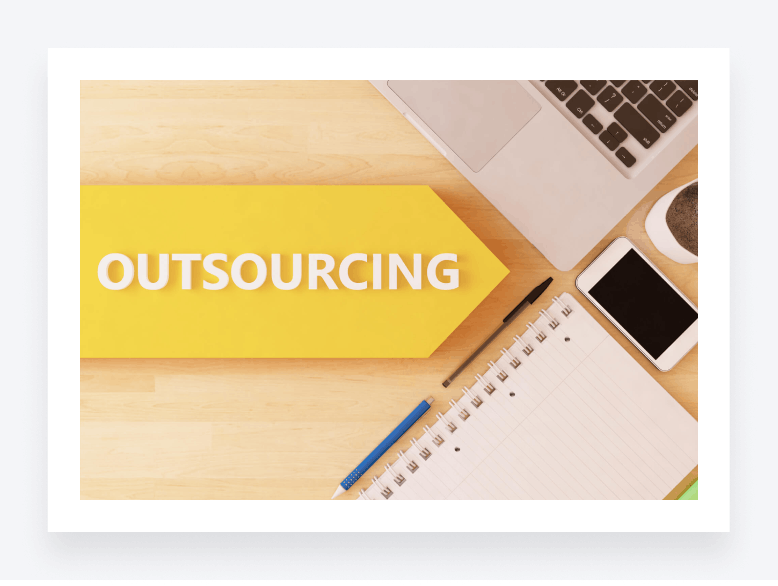
給与計算代行
給与計算代行は、給与計算を外部の業者に委託することです。タイムカードの集計から入退社や人事異動の情報更新まで行い、給与計算を代行します。残業代や社会保険料などの計算が含まれ、給与明細の作成や郵送なども依頼できます。
振込・納税代行
給与計算の結果の給与振込データ作成や振込、税金の納付を代行します。給与計算代行とセットで依頼することが多いです。
年末調整代行
年末調整は特に煩雑で繁忙期が年末から年初に集中するため、アウトソーシングサービスで依頼することも少なくありません。控除申告書類の封入・送付や申告書の内容確認、従業員からの問い合わせ対応、源泉徴収票や支払報告書などの作成と提出代行が含まれます。
住民税更新代行
住民税の更新は毎年5月から6月にかけて行われ、繁忙期が限られています。地方税である住民税は市区町村とのやり取りが必要で、特別徴収額通知書などの紙媒体を多く扱います。
通常、企業は給与計算代行やアウトソーシングの範囲を、自社のニーズやコスト意識に合わせて選択します。給与計算代行だけでなく、タイムカードデータのデジタル化や勤怠管理、社会保険・労働保険の手続きまでトータルでアウトソーシングすることもあります。
中小企業における給与計算のアウトソーシングの状況
従来は大企業や外資系企業での利用が中心でしたが、近年、中小企業でも給与計算代行を利用するケースが増えているとされています。理由としてクラウドサービスの普及によるサービスの価格低下が考えられます。
人事部門のリソース削減や効率化が求められる中、定年退職による人事担当者の減少もあり、給与計算や労務管理のアウトソーシングが活発化していると言われています。
中小企業の給与計算に関する課題として、給与計算業務が特定の担当者に集中しやすく、属人化しやすいことが挙げられます。中小企業では人事・労務部門が少人数体制で給与計算を担当しているため、担当者の負担が大きくなる傾向があります。その結果、繁忙期には担当者が過度に残業しなければいけない可能性が高まる上、担当者が突然退職すれば業務が停滞するリスクもあります。
担当者の負担が過重であれば、給与計算のミスが起こりやすくなります。給与計算の労働負荷は小さくなく、通常は他の業務と並行して処理する必要があるため、効率的な対応が求められます。さらに、社会保険料や控除項目の計算、法改正への対応などさまざまな対応が必要です。
会計事務所や社労士に給与計算を依頼するメリット・デメリット
給与計算業務を外部の専門家に依頼することで、さまざまなメリット・デメリットがあります。それらを具体的に説明します。
メリット
まずはメリットからご説明します。
業務負担の軽減
給与計算を外部に依頼すると、自社の業務負担が大幅に減ります。特に中小企業では、経営者や労務担当者が給与計算を兼務しているケースも多く、給与計算が本業の時間を奪う可能性があります。外部に依頼することで、主要業務に専念できるようになります。
専門人材の確保や異動・退職時の対応が不要
給与計算には源泉徴収税や社会保険、労働保険などの専門知識が必要です。自社で給与計算を実施するとすると、これらの専門知識を持つ人材を確保・育成しなければなりません。人材の異動や退職があると引き継ぎが困難になります。外部に委託すれば、社内に専任者を置かなくてもよく、業務の属人化も防げます。
法改正対応を任せられる
給与計算にはさまざまな法律が関係し、税金や社会保険料の料率も頻繁に変更されます。専門家に依頼すれば、最新の法改正に適切に対応してもらえるので安心です。
デメリット
社会保険労務士や税理士に給与計算を依頼することには多くのメリットがありますが、デメリットもあります。メリットとデメリットを両方理解してから検討しましょう。
情報漏えいのリスク
給与計算を外部の専門家に任せる際は、情報漏えいに注意が必要です。給与計算には勤怠データや扶養家族の人数など従業員の個人情報が含まれるため、依頼先のセキュリティ対策やデータ保護に関する方針を確認する必要があります。
ノウハウの蓄積が難しい
給与計算を外部に任せると社内の負担は軽減されますが、その分、社内にノウハウが蓄積されにくくなります。将来、社内で給与計算を自分たちで行おうとした際に、適切に進められる人材が不足する可能性があります。
費用がかかる
外部に給与計算を依頼すると、業務内容に応じた費用が発生します。費用は依頼先や従業員の人数、依頼内容などによって異なるため、事前見積もりを取って、どれぐらいの費用が発生するかを確認しておくとよいでしょう。
会計事務所・社労士の業務内容
会計事務所と社労士とでは得意とする業務内容がそれぞれ異なります。この章ではその違いについて解説します。
会計事務所
会計事務所が給与計算や年末調整の業務を担当することは珍しくありません。給与計算や年末調整は会社の経理処理において重要な部分であり、個人情報の取り扱いもあるためです。
給与計算は、給与の締め日から支給日までの間に計算を完了し、その結果を会社に伝えます。場合によっては、税理士が給与の振込手続きも行うこともあります。
社労士
社労士は社会保険や労務管理に関する指導や相談を行う専門家です。給与計算の代行を含む社会保険に関する業務に加え、社会保障法令や労働関連法令に基づく書類作成、提出、手続きも行います。また、労務管理のサポートを請け負うこともあります。
さらに、労働社会保険に関する申請業務や行政機関の調査に対する対応、顧問としての事務代理業務なども行います。
給与計算のアウトソーシングに適した企業
ここまで説明した給与計算業務のアウトソーシングに関するメリットとデメリットを踏まえて、アウトソーシングに向いている企業について説明します。
専門知識を持つ担当者がいない企業
給与計算業務は税務や労務のリスク、情報漏洩のリスクと隣り合わせで、法令に従い正確に行う必要があります。社内で行う場合は、専門知識を持つスタッフを確保することが重要です。法改正に随時対応し、6月や9月に住民税や社会保険料の納付金額を見直す必要があります。専門知識が必要なので、専門知識を持つ担当者がいない企業は給与計算のアウトソーシングに向いていると言えます。
担当者が本来の業務に集中できていない企業
給与計算業務を社内で行っているために、担当者がコア業務に集中できていない企業です。アウトソーシングを活用することで、人事部門は採用・評価・教育に、総務部門は社内環境の整備に専念でき、経営者は事業の成長に集中できます。
給与計算担当者が1人だけの中小企業
給与計算担当者が1人しかいない場合、休職や退職があった際に業務が滞る可能性があります。アウトソーシングを利用すれば、担当者の休職や退職があっても業務が滞ることなく、契約期間中は安定して業務を続けられます。
給与計算を依頼すべきは会計事務所か社労士か?
給与計算を依頼する際に、会計事務所と社労士のどちらを選ぶべきか迷ったときに注目すべきポイントを紹介します。
年末調整は税理士の独占業務
給与計算だけでなく年末調整の手続きも依頼したい場合は、会計事務所に依頼するとよいでしょう。
年末調整は会社が年末に行う手続きで、従業員の所得税の過不足を調整するものです。会社は従業員に給与を支払う際、所得税を源泉徴収していますが、この合計額は1年間に納めるべき税額と一致しないことが多いです。そのため、源泉徴収した所得税の合計額と納めるべき所得税を正確に算出し、差額を調整する手続きを行う必要があります。
年末調整の代行は税理士だけが行える独占業務で、年末調整に伴う法定調書の作成や提出も代行できます。したがって、年末調整の手続きも依頼したい場合は、給与計算を担当している税理士に依頼するとスムーズです。
役員報酬の決定には税の知識が必要
役員報酬を決める際は、会計事務所に相談するのがよいでしょう。
役員報酬は役員の給与に似たものですが、従業員の給与とは税法上の取り扱いが異なります。
例えば、起業1年目の場合、会社設立日から3か月以内に毎月の報酬額を決めないと、税法上の損金として計上できません。また、役員報酬は通常、事業年度ごとに改定されます。ただし、事業年度開始から3か月以内に変更し、1年間(少なくとも期末まで)決めた金額を固定して支給しなければ、全額を損金に計上できません。
役員報酬の金額は会社の法人税にも影響を及ぼします。役員報酬の決め方が税法に適合しているかどうかを確認するために、まずは会計事務所に相談するとよいでしょう。
会社設立直後や中小企業はまず税理士に依頼
一般的に、中小企業が給与計算を外部に依頼する際には、会計事務所に依頼することが多いです。これは、中小企業の多くが顧問税理士と契約しているためです。月ごとの会計処理や確定申告業務を契約しているので、単独で依頼するよりもコストを抑えて給与計算も外部に任せることができます。
さらに、従業員が少ない中小企業では、入退社や社会保険の手続きもそれほど複雑ではないため、税理士に依頼して年末調整などの手続きまで一緒にお願いする方が、メリットが大きいと言えるでしょう。
まとめ
管理業務の中で重要な給与計算業務は、自社の従業員に行わせるか、それとも専門性の高い外部組織に委託するかを選ぶ必要があります。
給与計算を自社内で行う場合とアウトソーシングする場合には、それぞれメリット・デメリットが存在します。企業の状況や人員配置、コスト、経営リスクなどの観点から、アウトソーシングを採用するかどうかは、経営陣が判断する必要があります。アウトソーシングするのであれば、まずは会計事務所に相談するとよいでしょう。
そして、会計事務所や社労士事務所を選ぶ際のポイントの1つとして、「TaxDome(タックスドーム)」に代表されるITツールの運用を含む、各事務所のDX化への取り組み状況があげられます。士業事務所のオペレーション効率改善、及び、事務所がカスタマーに提供するサービス品質の向上のために開発された「TaxDome」は、欧米を中心とした世界各国の士業現場において業務インフラ的に利用されており、日本においても導入する事務所が急速に増えています。利用する事務所を選ぶ際は、「TaxDome」の様なITツールの導入状況を含む、各事務所のDX化への総合的な姿勢を確認することがおすすめです。

eBookが送信されました。メールをご確認ください。
エラーが発生しました。再度お試しください。